オペアンプはアナログ信号を増幅するための基本のICです。
このオペアンプとディジタルIC(A/D変換など)をうまく組み合わせると、
色々な応用が可能となり、いよいよ電子工作が面白いものになります。
ここでは、このオペアンプの基本的な使い方、回路設計方法について
説明しています。
【オペアンプの基本】
オペアンプの基本を図で表すと下図のようになり、2ピンの「差動入力」
と1ピンの出力、それと+と−の2つの電源ピンからなっています。
基本的な動作は、差動入力の端子間の電圧の差が増幅されて
出力に現れるという動作です。
+入力側の方が電圧が高ければ
出力も+側となり、
−入力側が電圧が高ければ、
出力は反転してー出力となります。
しかし、この増幅する時の増幅度が無限大に近い大きさがあるため、
そのまま使ったのでは、ほんのわずかでも差動入力電圧があると、
出力は+か−の最大値に張り付いてしまい、実用的に使えるアンプ
とはなりません。
しかし、この増幅度が無限大に近いということが大きなメリットとなる
方法があります。これが「ネガティブフィードバック」という方法です。
日本語では「負帰還」といいます。
(1)反転増幅回路
最も原理的なネガティブフィードバックを実現する回路が下図です。
これを、入力に対して出力の±の極性が反転するので、反転増幅
回路と呼びます。
ネガティブフィードバックを
実現する基本回路。
(反転増幅回路)
フィードバックはR2で行わ
れています。
この回路では出力から−入力側に抵抗R2を介して信号が戻るように
なっています。これをフィードバックといいます。さらに戻って来る電圧
は極性が逆になっているので、ネガティブフィードバックと呼びます。
こうすると、無限大の増幅度ですから、差動入力に少しでも差があると、
オペアンプの出力となって現れます。 しかし直ぐ、出力が入力側に
フィードバックされ、しかも極性が反対側になっているため、出力が
出ないよう、つまり差動入力の差が無くなるように働きます。
結果的にオペアンプの差動入力はいつも同じ電圧になるように動作
することになります。これを「イマジナルショート」と呼んでいます。
このイマジナルショートの部分が実際に接続されていると仮定して
回路を簡単化すると下図のように簡単になってしまい、抵抗の比だけ
で増幅度が決定されてしまいます。
a点で仮想的に接続されているとすると
両方向からの電流の和がゼロという
ことですから、左図の式のようになり、
オペアンプ回路の増幅度(A)は
A = R2/R1
ということになります。
これが、オペアンプの最大のメリットで、増幅度が抵抗の比だけで
決まるため設計が非常にやりやすくなります。
(2)非反転増幅回路
上記の反転増幅回路に対して、下図のように、入力と出力が同じ
極性になるようにしたネガティブフィードバック回路を非反転増幅
回路と呼びます。 この時には、入力と出力が同じ極性となるので
実際に使う時には扱いやすい回路となります。
(1)の反転増幅回路とは、
差動入力のプラスマイナス
が逆なことに注意して下
さい。
この回路を(1)と同じ様にイマジナルショートを使って簡単化すると、
下図のように考えることが出来ます。
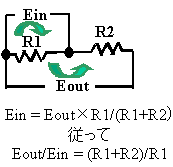
左図のように、電圧は同じ向きです
から、Eoutを分圧したらEinと同じになる
ということから、
非反転増幅回路での増幅度(A)は
A = 1+R2/R1
となります。
【オペアンプの規格表の見方】
オペアンプの規格表の見方では下記がポイントになります。
(1)電源の最大定格
何ボルトまで使えるかということになります。多くのオペアンプが
±15Vまでは一般的に使えますが、それ以上の電圧で使う時には
特に注意が必要です。
(2)しゃ断周波数(利得帯域幅積、単一利得帯域幅ともいう)
電圧増幅度が「1」になる上限の周波数のことを言います。
この値と周波数特性のグラフから、使える最大周波数が分かります。
(3)最大出力電圧
本当は電源電圧一杯まで出力が出来るのが理想なのですが、実際
には、電源より少し低い電圧までしか出力電圧は出ません。
これを気にしておく必要があります。
(4)単電源動作が可能か
多くのオペアンプは±の2種類の電源を必要としますが、特に
単電源で動作するように考えられたオペアンプもあります。
必要な場合にはそれを選択します。
下図は実際のオペアンプの規格表で、上記以外に多くの特性があり
ます。また、多くの特性がグラフ化されて規格表に掲載されています。
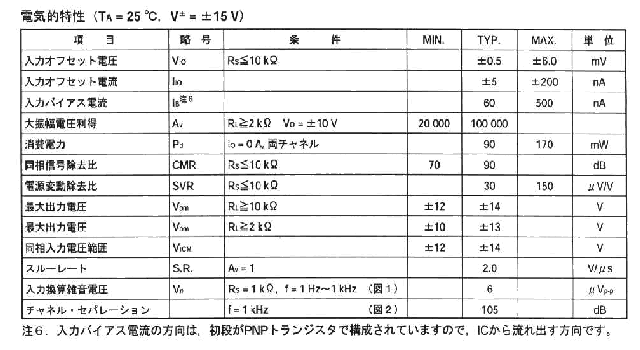
下図は、オペアンプの周波数特性で、図から分かるように、増幅度が
1(0dB)の時には2MHzまで使えますが、増幅度が10(20dB)の時には
200KHz程度までしか使えません。
【低周波増幅回路】
直流から10KHz以下の低周波信号の増幅回路を考えます。
A/D変換のために、センサの信号などの微小な電圧の信号を増幅し
ディジタル回路で検出可能な電圧とします。
上記で説明したように、出力を入力信号と同じ極性にするかしないか
で、2種類の基本回路がありますが、ディジタル回路への入力として
は、通常は非反転増幅回路を使って、正入力で正出力になるように
します。
また、ディジタル回路と電源が共用できるようにすれば、全体の回路が
簡単化されますから、5V単電源用のオペアンプを使います。
私がこの目的で良く使うオペアンプは、ナショナルセミコンダクタ社の
「LMC662」というICで下記のような規格となっています。
・供給電源電圧範囲 4.75〜15.5V (V+−V-)
・出力電圧範囲 0.17〜4.87V (typ at 5V電源)
・利得帯域幅 1.4MHz
これで判るように単電源での動作を前提にしたICで、出力電圧も
Rail-to-Railといってほぼ電源電圧近くまでフルスウィングします。
周波数特性は余り良くないので、数10KHz以下での使用となります。
このICをA/D変換などのプリアンプとして使う時には、プラスの
微小信号をやはりプラスの出力にすることになりますので下図
が基本回路となります。(非反転増幅回路)
上記が基本的な回路で、R1とR2は差動入力のバランスが取れる
ように同じ値を使います。
増幅度(A)が調整出来るよう可変抵抗R4を使いました。
各抵抗の決め方は、まずR1、R2を決めます。
R2は単にバランスを取る為だけにあり、回路定数には影響しません。
R1,2は入力源となるセンサなどが要求する負荷抵抗で決めますが、
大体数KΩが一般的な値となります。 LMC662の入力インピーダンス
は、とてつも無く大きな値(10の12乗)ですから無視できます。
あとは必要な増幅度(A)から(R3+R4)の値が決まります。
R3とR4の割合は増幅度の調整範囲をどれぐらいにするかで決めます。
余り広い調整範囲とすると可変抵抗を正確に調整するのが難しくなる
ので、10%〜30%くらいの範囲にします。
直流から低周波の信号の大きさを判定して、ディジタル回路にHigh/Low
で伝達するための回路で、オペアンプの仲間である「コンパレータ」という
アナログICを使います。
オペアンプの原理と同じですから、非常に大きな増幅度であり、差動入力
のほんのわずかの差を検出することが可能です。
しかし、余り感度が良すぎても使いにくいので、丁度適当な感度にする
ためのテクニックがあります。
それが「ポジティブフィードバック(正帰還)」と呼ばれる方法です。
この回路は、シュミット回路とか、ヒステリシス回路とも呼ばれています。
基本的な回路構成は下図のようにし、基準電圧Etが比較の基準になり
ます。
この回路では、出力電圧のR2とR3による分圧した電圧がヒステリシスと
なり、出力を反転させるためには、入力は基準電圧より、このヒステリシス
分だけ余分に差が必要です。
ヒステリシス Eh=(Eout−Et)×R3/(R2+R3)
このことにより、ノイズなどのわずかの電圧差でコンパレータが動作して
不安定になるのを防ぐことが出来ます。
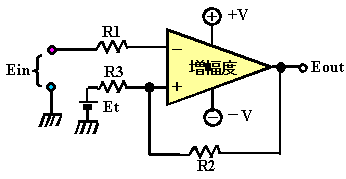
ヒステリシスの値は下記で求められます。
実際のR1,2,3の値の決め方は、R1とR3はバランスをとるため同じ値と
します。通常は数KΩを使います。
あとはヒステリシスをどの程度にするかでR2を決めますが、普通では
このヒステリシスは数10mV以下とします。
《実際のコンパレータ回路》
実例として、5V単電源で入力電圧が1Vを基準にした、コンパレータ
回路を考えてみます。
まず基準となる1Vは電源電圧を抵抗で分圧してつくることとします。
使うコンパレータICはモトローラ社の「LM393」です。
このICの出力はオープンコレクタとなっていて出力のプルアップ抵抗
が必要になりますが、コンパレータを5Vより高い電圧で異なっていても
次段に接続するディジタルICの電圧に合わせることが出来て便利です。
実用回路は下図のようになります。
12Kと3Kの抵抗で5Vを分圧して基準の1Vとしています。
ここでヒステリシスは、出力電圧が5Vのときに、数10mV程度になるよう
に10KΩと1MΩで1/100としています。
結果として、出力が1→0になる時は約40mV、0→1になる時は約10mV
のヒステリシスとなります。